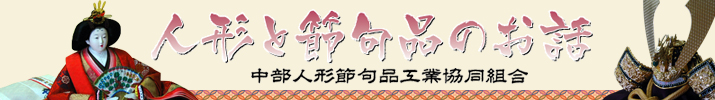江戸時代になると「貞丈雑記」に「こぎのこ、こぎ板という物を、今江戸にてははごのこ、はご板というなり」とあります。
このように、なぜ「こぎ板」「羽子板」とよばれるようになったか詳かではありませんが、もとは「子木板(こぎいた)」でこれに羽根が付いて「羽子木板(はこぎいた)」となり、これが略されて羽子板になったという説もあります。
突く羽根の黒い玉は「木蓮子(むくろじ)」で「無患子」とも書き、これに穴をあけて羽根をつけたものです。これを突き上げるとたしかにとんぼのような動きをしますが、蚊のいない正月に蚊に食われないまじないというのも今一つしっくりきません。羽根突きは室町時代にも正月の遊びとされていますので、これは後からつけられた理由のようです。
江戸時代に江戸ではこの羽子板に人気歌舞伎役者を押し絵で描くことか流行し、現在の羽子板に発展しました。
美しい羽子板が作り出され、遊びの道具としてだけではなくお正月の飾りとして欠かせないものとなったのもこの頃からです。
初正月の女の子のお祝いとしてよく贈られますが、毎年お正月に玄関やお部屋にお飾りいただいたり、お座敷やお茶席のお正月の縁起物としてお飾りいただくのもいいものです。
|